10月3日(木),第2回生徒会総会が開かれました。総会に先立ち,後期役員の任命が行われ,本格的に後期組織がスタートしました。総会では,平尾暁絵さん(3年)と大沼櫂君(1年)の2人が議長を務め,前期生徒会活動報告と後期活動計画が審議されました。各委員会の報告に対していつくか質問があり,担当生徒が答弁する場面が見られ,生徒自らが主体的に生徒会活動について考える時間となりました。後期生徒会役員には,自分たちの学校を自分たちで良くしていくという意識を継続しながら,裏中生徒会の伝統をさらに発展させる取組を期待しています。



10月3日(木),今年度も何度か合唱の指導をお願いしている早川先生にご来校いただき,友絆祭に向けた合唱指導していただきました。1学年50分ずつ,3学年で3時間みっちりご指導していただき,各学年の課題曲を練習しました。発声の方法から具体的にご指導いただいたので,生徒たちの今後の練習にも生かすことができる,貴重な時間となりました。友絆祭では,1年生は「君をのせて」,2年生は「糸」,3年生は「手紙~拝啓 十五の君へ~」を披露します。また,毎年恒例の早川先生のミニコンサートも実施いたします。地域の皆様,保護者の皆様,友絆祭での合唱にご注目を!



10月2日(水)に,2・3年生が諸橋近代美術館を訪問し,ダリを中心とした近代的な美術品を鑑賞しました。生徒たちは,偉大な芸術家の作品を間近で見て,その創造力,構成力のすばらしさに感動していました。学芸員の方々に説明をしていただきながら案内していただきましたので,作者の思いや時代背景なども聞けて本当に有意義な時間となりました。今後も県内でも有数の地元の美術館を訪問させていただき,子どもたちに「本物に出会える」ことのすばらしさと感動を味わわせたいと考えております。美術館のスタッフの方々のお心遣いに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

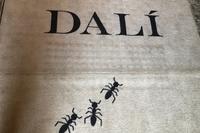

10月1日(火),本校に裏磐梯小学校6年生5名に来ていただき,授業や部活動を見学してもらう取組を行いました。児童たちは,理科,音楽,保健体育の3つの授業を参観したあと,バドミントン部と陸上部の部活動を見学しました。部活動見学では,実際に走ったり,ラケットで打ったりと体験活動も行われました。来年4月に入学する子どもたちに,中学校生活の雰囲気を多少なりとも味わってもらえたと思います。



9月27日(金)の午後に,裏磐梯幼稚園,裏磐梯小学校,裏磐梯中学校の3校合同で,クリーンアップ活動を行いました。子どもたちと先生方を8班に分けて,ビジターセンター方面や小野川湖方面,学校周辺,噴火記念館方面などを歩きながら,ごみを拾いました。中学生が班長になり,小学生と幼稚園児をまとめる姿が見られ,とても頼もしく感じました。自分たちが住む地域をきれいにするという意識が高まったと思います。



9月25日(水),26日(木)の2日間,耶麻中体連新人大会が開催され,本校バドミントン部1・2年生が出場しました。3名のバドミントン部に2名の特設バドミントン部の生徒を加えた5名の生徒がシングルスの試合に出場し,2種目で優勝することができました。3年生の先輩方が引退してから,少ない部員で練習を頑張ってきた成果が出た大会だったと思います。今大会の反省をしっかりして,10月12日(土)・13日(日)の全会津新人バドミントン大会に臨みたいと思います。保護者の方々からも大きなご声援をいただき,ありがとうございました。
【大会結果】
男子シングルス 優勝 佐藤 陽向大(2年)
第3位 渡部 裕樹(2年)
ベスト8 松本 安友武(2年)
女子シングルス 第2位 安部 優花(2年)
1年男子シングルス 優勝 三浦 和貴(1年)



本日,今週の各学年の学年通信を発行いたしました。内容は,生徒会立会演説会,会津新人陸上の結果,校内高校説明会,早稲沢農業体験など多岐にわたっています。先週から今週にかけて行事が大変多く,子どもたちの活躍が目立った週でした。
来週は,耶麻中体連新人大会にバドミントン部1・2年生が出場します。新チームになり,最初の公式大会ですので,生徒たちがどのくらい活躍してくれるのか大変楽しみです。また,中間テストの前の週でもあり,まさに文武両道が求められます。勉強と部活動,両方頑張ってくれることを期待しています。
第1学年通信20号 .pdf
第2学年通信20号.pdf
第3学年通信20号.pdf
裏磐梯中学校だより「友絆」9月号を発行いたしました。
内容は,2学期始業式の様子と,耶麻地区合唱コンクール,英語弁論大会,全会津駅伝大会の生徒の活躍などです。
2学期が始まり約1ヶ月が過ぎましたが,子どもたちは毎日,勉強や部活動に全力で頑張っております。学校行事や各種大会・コンクールでは,生徒たちは,自分の目標を明確にしながら取り組み,大きな成果をあげることができました。保護者の方々にも生徒の活動を応援していただき,心から感謝しております。今後も,学校と地域・家庭が協働して,子どもたちのために尽力していきたいと思いますので,ご理解とご協力をお願いいたします。
